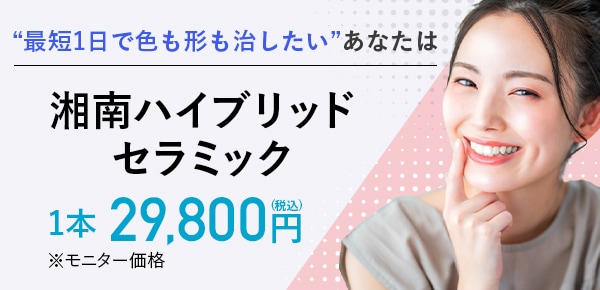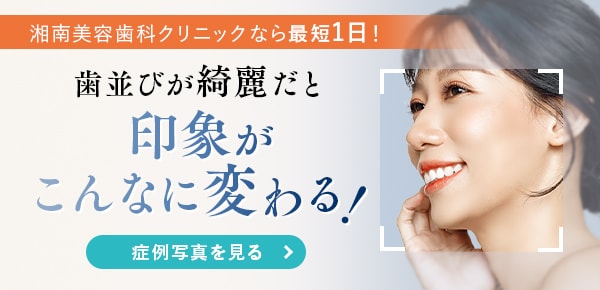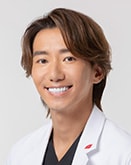目次
歯並びによる噛み合わせと噛み癖が体の歪みへと影響します

歯並びが悪く噛み合わせが悪いことによって食べ物を片側のみで噛むという習慣がつくと、噛んでいるのとは反対側にある頚椎周辺の筋肉が強く働くようになります。
すると、そちら側へ頭部が傾いたり頚椎が引っ張られたりすることで頸部の歪みが起こります。
これは体の左右の重さのバランスを変化させ、これを中心に引き戻すために頚椎以下にある背骨周辺の筋肉の働きも変化して背骨の歪みにつながります。
歯並びは噛み合わせや顎関節に影響します
以前は歯の白さに注目が集まっていたように思いますが、近年は歯並びを気にする人が非常に増えてきています。
人との会話や笑ったときに相手から見える部分であるだけに気にする点であることはもちろんですが、食べ物の欧米化で顎の発達が不十分であるために、歯並びが悪いといわれる人が増えてきていることも理由の一つと言えるでしょう。
しかし、歯並びは見た目だけでなく、噛み合わせや顎の関節にも影響を及ぼします。
歯並びが悪い状態にあると、口を閉じた時に上の歯と下の歯の接触も悪くなります。
正しい噛み合わせは、下顎列にある前歯が上顎列にある前歯よりもやや後方にあって、上顎列の歯の先端のやや内側に接し、奥歯である臼歯も上下が同じ力で接触できるようになっています。
歯並びが悪くなると、これらの位置関係が変化します。
例えば、一部の歯が強く接触する一方で、他の歯の間には隙間ができることがあります。
噛み合わせが悪いことで前歯で食べ物を噛み切ることができなくなると、自然と奥歯で食べ物を噛むことが増えてきます。
また、臼歯の接触に左右差があると無意識に食べ物を片側のみで噛むことが増えてしまいます。
食べ物を噛むときに歯にかかる力は、非常に強いといわれています。
その力が片側のみに集中すると、咀嚼筋にかかる負荷も集中しますし、顎の関節にも負担が集中するために、顎関節症をおこすことにもつながるのです。
片側で噛み続けることは顎関節だけではなく頸を含む背骨へも影響します

「噛む」という動作では、下顎骨のみが動いているようにも見えますが、実は自分でも気づかないところで筋肉が働いています。
食べ物を噛む際は下顎骨を一旦下へ引き下げた後に上へ持ち上げるという動きが起こります。
下顎骨を下へ引き下げる際は、下顎骨から喉にある舌骨へ走行する筋肉が働きます。
この筋肉が下顎骨を下へ引き下げる際、頚椎につく舌骨とそこからさらに鎖骨へと伸びる筋肉だけが働くと頭部も下顎骨と共に動いてしまうため、これを固定するために頚椎後方にある筋肉が作用します。
その後、咀嚼するために下顎骨を引き下げますが、この時も頭部を固定しないと咀嚼筋の作用で頭部が前下方へと引っ張られてしまうので、やはり頚椎後方の筋肉が働くことになります。
さて、片側のみで噛むことを続けていると、それとは反対側の頚椎後方の筋肉が働くようになります。
頚椎周辺は非常に細かな筋肉が多く、その筋肉は左右対称についていますが、片側のみが働くようになると、その筋肉が頚椎をそちらの方向へ引っ張るようになってしまいます。
例えば、右側のみで食べ物を噛んでいると、頚椎後方左側にある筋肉が強く働くことが増えるため、頚椎が左側へ引っ張られるようになるのです。
背骨は細かな骨が積み木のように積み重なっている部分ですので、片側のみの筋肉が働くようになると背骨がそちらへ引っ張られたり、頭がそちらの方向へ傾くようになってしまうのです。
頭部から頚椎の歪みはやがてその下の背骨へと波及します
頚椎の歪みや頭部の傾きは、その後それより下にある背骨へと影響を及ぼします。
頭部は体の最も上についていながら、5kgもの重さがあるところですが、これが例えば右に傾くと本来左右対称にかかっているはずの重みがやや右側へシフトします。
体が右側へ倒れる方向に重みがずれるのです。
そのままでは体は右に倒れやすくなってしまうので、頚椎以下の胸椎レベルや腰椎レベルでは体の重みを中心方向へと引き戻すために、背骨左側の筋肉が強く働くようになります。
胸椎は肋骨と共に胸郭を形成しているので比較的固定されていますが、腰椎は周辺で固定してくれるものが筋肉しかありません。
その筋肉が片側のみ強く働いてしまうと、今度は腰椎をそちらへ引っ張るようになってしまうのです。
歯並びによる噛み合わせの変化や、片側のみで食べ物を噛むという噛み癖は、筋肉の働きを通じて背骨へも影響を及ぼします。
この癖を治すためにも歯並びを矯正し、噛み合わせを整えることで、左右どちらでも噛むことができるようになります。
これにより、バランスよく筋肉を使えるようになり、体の歪みの改善も期待できます。
- 関連記事:歯並びを悪くする寝相とは?
- 体の歪みは日々の寝相が影響する場合もあります。
(まとめ)歯並びと体の歪みは関係があるの?
歯並びは噛み合わせに影響し、噛み癖がつくと左右対称についている背骨周辺の筋肉の片側が強く働くようになります。
これが頚椎の歪みのみならず背骨全体へと波及し、最終的に体の歪みへと影響を及ぼすことになります。
歯並びの不良は噛み合わせに影響しますが、これによって食べ物を噛む際に片側の奥歯のみで噛むことが増えてしまい、片側の咀嚼筋や顎の関節にも負担を掛けることになります。
長期間続くと、顎関節症に移行する危険性も持っています。
片側のみで噛むことを続けていると、下顎骨の動きに対して頭部を固定するために反対側の頚椎後方の筋肉が強く働くため、頚椎がそちらの方向へ引っ張られたり、頭部が傾いたりするようになってしまいます。
頚椎の歪みや頭部の傾きは、それより下にある背骨の歪みへと波及します。
歯並びを整えて左右両側で噛むことができるようになると、背骨周辺の筋肉も左右バランスよく働くようになり、体の歪みの改善にもつながるのです。