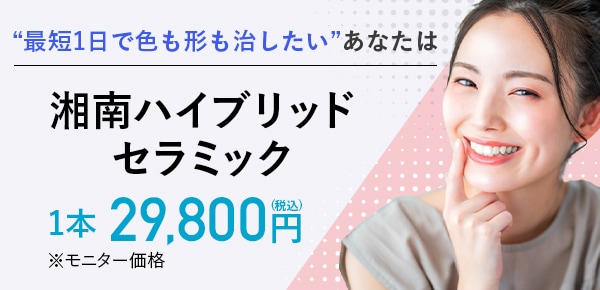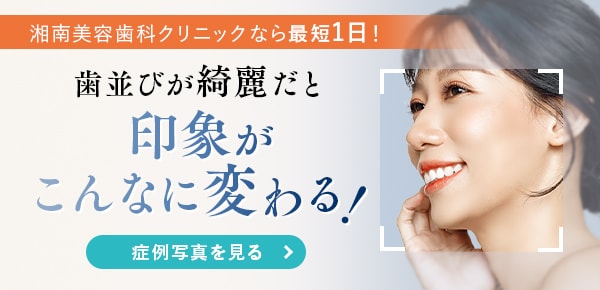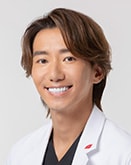目次
歯並びとろれつには直接的な関係もあれば間接的に関係する場合もあります

歯並びが悪いことで、一部の音(言葉)を正しく発音できない、いわゆる「ろれつが回らない」という状態になることがあります。
この場合、歯並びを修正することで、問題は解決できるようです。
その一方で、ろれつが回らないことに関しては舌側に原因があり、その原因が歯並びに影響を及ぼす場合もあります。
歯並びが悪いと一部の言葉を正しく発音できなくなることがあります
「ろれつが回らない」というと、一般的には例えば脳卒中になったときのように、舌や唇が正しく動かず、言葉を正しく発音できないために、話していることが相手にとって聞き取りづらい場合を想像するかもしれません。
けれど、「言葉を正しく発音できない」という点でいうと、脳卒中以外の場合も起こり得るようです。
例えば、下顎の歯よりも前歯が明かに前に突出している「上顎前突」や、その逆である「下顎前突(受け口)」、さらには、奥歯は噛みしめているのに前歯がかみ合わず隙間が開いている「開咬(かいこう)」などがそうです。
本来、上下の歯を噛み合わせた状態のところから空気を押し出して発音する「さ行」が、正しく発音できなくなります。
また、前歯の歯並びがガタガタになっている叢生(そうせい)や乱杭歯(らんくいば)、八重歯などがあると、「た行」や「な行」、「ら行」など舌先を上列前歯の裏側に当てて発音する言葉が不明瞭になります。
ちなみに、「ろれつ」と似た意味で用いられる言葉に「滑舌」がありますが、こちらは発音の問題というよりも、「話をするときに言いよどむことがなく、流れるように話す」という意味がありますので、ろれつとは少々意味が異なります。
- 関連記事:歯並びが悪いと滑舌にも影響する?
- 歯並びが滑舌に及ぼす影響についてはこちらの記事でご説明しています。
ろれつが回らない原因が歯並びの悪さをもたらすこともあります

ろれつが回らないという場合、舌の動きが悪いことが原因となる場合もあります。
わかりやすい例として、お酒を飲んで酔っ払ったときなどでは、舌の動きが悪くなることで、言葉が不明瞭になることがあります。
先ほども挙げた「た行」や「な行」、「ら行」は、上列の前歯の裏側に舌先を当てて発音するため、舌の動きに可動性が必要になります。
ところが、この舌の動きが制限される場合があります。
舌先を喉の方へ巻き込むと、舌の裏側にピンと張った膜のようなものがありますが、これを舌小帯と言います。
これが短い、あるいは舌先に近いところまで張っている「舌小帯短縮症」というものがあるのですが、これがあると舌を上顎の方へ動かすことが不自由になるために、た行やな行、ら行の発音が難しくなります。
これに加え、口を閉じた状態では本来上列前歯の裏側についているはずの舌が、下顎の中に収まっている状態が常になるために下列の前歯が舌で押され、歯が前方に突出する受け口になることにもつながります。
舌小帯短縮症は後天的に起こるものではなく、通常は生まれた時からそのようになっていることが多いようです。
歯並びを良くするとろれつも改善する可能性があります
もし、言葉の発音が不明瞭である原因が、舌小帯短縮症である場合は、舌小帯を少し切ることで改善できるでしょう。
ただ、すでに下顎前突を伴っている場合には、これに対する施術も必要になります。
また、言葉の不明瞭さが歯並びにある場合には、歯並びを改善することでろれつの回復も可能であるかもしれません。
上顎前突や下顎前突には、いくつかの原因があります。
一つは顎の骨そのものの大きさに問題がある場合です。
下顎前突の場合、上顎の骨に対して下顎の骨が大きく前にせり出していることが一つ目の原因、もう一つは顎の骨の大きさに比して歯が大きいために、前にせり出してしまっている場合です。
また、顎と歯の大きさのバランスは良いのですが、歯が前にせり出してしまっている場合にも、下顎前突になります。
単に歯が前にせり出してしまっていることが原因の場合には、クラウンを使って歯並びを整える方法があります。
また、顎の骨と歯の大きさのバランスが悪いという場合は、状態によっては一部を抜歯して矯正を行うことがあります。
さらに、下顎の骨が前にせり出してしまっている場合には、顎の骨に対して外科的な治療が必要になることもあります。
(まとめ)歯並びは話す時のろれつに影響するのでしょうか?
歯並びの悪さは、一部の音が発音しづらくなることで、いわゆる「ろれつ」に影響します。
また、ろれつが回らない原因が歯並びに影響を及ぼすこともあり、この場合にはその原因を取り除くことが必要になります。
上顎前突(出っ歯)や下顎前突(受け口)、開咬の場合、「さ行」の発音が悪くなります。
また、歯並びがガタガタの状態になると、「た行」や「な行」、「ら行」などを発音する際に歯と歯の隙間から空気が漏れてしまい、正しく発音できなくなることがあります。
舌小帯短縮症があると、舌の可動性が悪くなり、一部の言葉の発音に影響します。
さらに、閉口時の舌の位置が下顎にあるため下列前歯が舌先で押され、これが前に突出する下顎前突(受け口)の原因にもなります。
歯並びを整え、上下の歯の位置関係を良くすることで、ろれつを改善できる可能性があります。
また、舌小帯短縮症が原因でろれつがはっきりしない場合は、これの一部を切離することで改善を図ることもできるようです。